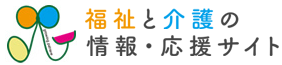問題36 次のうち、諸外国の精神保健医療福祉領域において資格化されている人材として、正しいものを1つ選びなさい。
1 ニュージーランドにおける地域支援ワーカー
2 韓国における社会工作師
3 アメリカにおける認定ソーシャルワーカー
4 イギリスにおける認定ピアスペシャリスト
5 中国における精神保健専門要員
一読してこの問題は解けないと思った人は、ここで時間を浪費してはいけない。
知らないと解くのは難しい。
1は、〇である。
2は、×である。社会工作師は中国である。
3は、〇である。
4は、×である。
5は、×である。精神保健専門要員は韓国である。
【正解1,3】(※試験ではいずれかを選んでいれば正解とされた)
韓国-精神保健専門要員または中国-社会工作師のいずれかを知っていれば、肢2と肢5を交差法で×であろうと推測できる。
ただし、普通に勉強していてもあまり目にしない知識ではないだろうか。
肢1,肢3,肢5の中では、肢3を選ぶ人が多いと思われるが(アメリカでのソーシャルワーカーが活躍していることは知っているし、認定制度も同国らしいので)、知らないと自信を持っては解答できない。
しかも、問題文では、正しいものを1つとなっているのに、試験結果発表の際に肢1と肢3のどちらも正解とされた。
試験場では、本問に関する知識を有しており、きちんとわかっていた人が、もっとも迷ったのではないだろうか。
問題37 人口40万人のN市では、市の自殺対策推進計画に基づいて、市保健所が中心となり自殺対策を推進している。中学生の自殺報道が続いたため、市の中学校関係者や住民より、「自殺の連鎖が起こらないよう、取組を強化してほしい」と、市保健所へ要望が相次いだ。自殺対策の担当であるG精神保健福祉相談員は、市自殺対策推進会議で、児童生徒など若年層への予防的取組の強化を提案することとした。
次の記述のうち、この時点でのG精神保健福祉相談員の提案内容として、適切なものを2つ選びなさい。
1 教師を対象とした、ゲートキーパーの養成研修を開催する。
2 自殺の相談は、保健所での来所面接で一括して対応する。
3 自殺の危険性が高い人の早期発見は、精神保健福祉士の固有の役割であることを広報する。
4 メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教育及び違法•有害情報対策に協力する。
5 自殺の連鎖を防ぐため、自殺の場所や手段などの詳細を繰り返し伝える。
リテラシーの意味がわからずに、悩んだ人もいると思われるが、試験では正解が導ければよい。
本問は、消去法でも答えが出せるので、細かい点にこだわって時間をロスしないようにしてほしい。
1は、〇である。まずは、教師にゲートキーパーとなってもらうため、養成研修を開催するのは、一つの方法だと考えられる。仮に、迷っても△くらいにしておくべきだろう。
2は、×である。自殺の相談なのに、来所面談での一括対応というのは、適さないだろう。メールや電話など、柔軟かつ個別に対応するべきである。
3は、×である。自殺の危険性が高い人の早期発見は、
精神保健福祉士の固有の役割とはいえない。
4は、〇である。自殺報道を聞いて、どのように受け止めるのかについてのリテラシーは役立つといえるし、自殺を助長しかねないような報道に対しての情報モラル教育及び違法•有害情報対策への協力は、G精神保健福祉相談員の提案内容として適切であろう。
5は、×である。自殺の場所や手段などの詳細を繰り返し伝えることは、かえって自殺の連鎖を助長する危険性がある。そもそも、「中学生の自殺報道が続いたため、市の中学校関係者や住民より、「自殺の連鎖が起こらないよう、取組を強化してほしい」と、市保健所へ要望が相次いだ」のであるから、このような対応が不適切であることは何となくわかるのではないだろうか。
【正解1,4】
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
リテラシー( literacy )の原義は「読解記述力」を指し、そこから転じて現代では「(何らかの形で表現されたものを)適切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現する」という意味で使われている。
最近になって、情報リテラシーや金融リテラシーといった言葉を耳にすることが多くなった。
問題38 次のうち、アンソニー(Anthony, W.)らの提唱した精神科リハビリテーションの基本原則に関する記述として、適切なものを1つ選びなさい。
1 様々な技法を駆使するよりも、特定の技法を適用する。
2 障害のレベルに応じて、本人の参加の可否を判断する。
3 生活能力の向上よりも、症状の軽減を優先する。
4 熟慮した上で依存を増やすことは、結果的には本人の自立につながる。
5 本人の技能開発の積み重ねが、回復の十分条件となる。
近時の試験では、2つまでは絞れるがそこから1つに絞る段階で悩む問題が増えている。
難しい問題だと感じるが、十分な知識がない場合、選択肢をよく読んで推論しながら解くしかない。
1は、×である。本人にとってよい結果をもたらすなら、特定の技法にこだわる必要はない。2は、悩んだ人も多かったのではないか。例えば、リハビリテーションプログラムへの参加について、個々人の障害のレベルを考慮することはありうることだと思われる。とりあえず、△とする。
3は、×である。積極的に本肢が×だとは感じられないかもしれないが、「症状の軽減を優先する」のなら治療だけでも十分だと言える。精神科リハビリテーションの基本原則というのであれば、生活能力の向上にも、力点を置くべきだ。
4は、〇である。アンソニーの精神科リハビリテーション基本原則を覚えていた人であれば、その一つに、「自立につながる依存」があったことに気付くだろう。知らなければ、△とする。
5は、×である。回復の必要条件となる。
【正解4】
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス
アンソニーの精神科リハビリテーションに関する知識がない場合の消去法
恐らくは、肢2か肢4の2択までは絞れるだろう。ここで、いずれがより、解答に近いかを吟味する。
肢2について改めて考えると、障害のレベルに応じて参加の可否を判断するよりも、参加してもらった上で、支援の内容を変えるという方法も考えられる。
もちろんプログラムの内容にもよるだろうが、初めから参加できないとしてしまうと、その先の支援が行き詰まるのではという疑問が湧く。
次に、肢4についても改めて考えてみる。
精神科領域の病は、病気と障害が併存しているところに特徴があり、どうしても依存しなければならない部分が残りやすい特質がある。そうした場合に、熟慮の上で依存する部分を増やすことは、結果的には本人の自立につながるといえる。
例えば、病気や障害を抱える人が、誰も助けも求めずに、全て自己完結を目指すより、誰かに助けを求めた方が(他人に依存する部分を作った方が)、より自立した生活の実現に近づくとイメージすれば、分かり易いのではないだろうか。
このように考えて、2<4と判断する。
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
アンソニーら(米)の提唱した精神科リハビリテーションの基本原則は重要であり、この際に復習しておくのがよい。
アンソニーらは、精神科リハビリテーションの役割を「長期にわたり精神障害を抱える人がその機能を回復するのを助け、専門家による最小限の介入で、自分の選んだ環境で落ち着き、満足できるようにすること」とし、その介入方法として当事者の技能開発と環境的支援開発の2つを挙げている(精神保健福祉士過去問解説集2016(中央法規)p425)。
◆アンソニー「精神科リハビリテーションの原則」
①精神障害を抱えた人の能力の改善
②環境における当事者の行動の改善
③様々なテクニックと臨機応変な対応
④職業上の予後の改善
⑤不可欠な要素としての希望
⑥自立につながる依存
⑦当事者の参加
⑧当事者の技能開発と環境的支援開発
⑨薬物療法(必要条件であるが、十分条件ではない)
問題39 次の記述のうち、精神科デイ・ケアにおけるリワークプログラムとして、適切なものを1つ選びなさい。
1 職場復帰してから開始する。
2 病気の再発防止よりも、作業能力向上を目指す。
3 プログラム終了の判断は産業医が行う。
4 グループワークで、職場の人間関係の課題が再現された場合に気付きを促す。
5 本人の同意の有無にかかわらず、情報は精神科デイ・ケア内にとどめる。
リワークとは、return to workの略語である。
1は、×である。むしろ職場復帰する
前に開始するのが通常である。
2は、×である。病気の再発防止の方が重要であることは容易に判断できるだろう。
3は、×である。リワークプログラムは職場に復帰するプロセスの中で行われるのだから、プログラム終了の判断を「産業医」が行うのはおかしい。
4は、〇である。精神科デイ・ケアにおけるリワークプログラムとして、適切といえる内容である。
5は、×である。本人の同意があれば、主治医などの関係者に伝えたほうがより本人の利益にかなう場合がある。
【正解4】
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
リワークプログラムとは、うつ病などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し、職場復帰に向けたリハビリテーション(リワーク)を実施する機関で行われているプログラムのことである。
問題40 次の記述のうち、包括型地域生活支援プログラム(ACT)の標準モデルとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 軽度の精神障害者で、かつ本人の希望があれば利用できる。
2 ケアの提供は日中を基本とし、夜間や休日は他機関に委ねる。
3 担当者が不在の時にも、多職種チームがケアを提供する。
4 利用開始時に期限を決めて、短期間で支援を終結する。
5 仲介型のケアマネジメントを基本とする。
(注) 包括型地域生活支援プログラム(ACT)の標準モデルとは、「ACTの標準モデル-ACT全国ネットワーク」(ACT全国ネットワーク発行)の内容とする。
包括型地域生活支援プログラム(ACT)の内容について多少なりともわかっていれば、正解を選ぶことは容易であろう。
【正解3】
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
包括型地域生活支援プログラム(ACT)とは、重い精神障害をもった人であっても、地域社会の中で自分らしい生活を実現・維持できるよう包括的な訪問型支援を提供するケアマネジメントモデルのひとつである。
1970年代初頭にアメリカで生まれてから多くの国に普及し、その効果が実証されている。ACTとはAssertive Community Treatmentの頭文字である。
問題41 次の記述のうち、精神保健福祉士が行う援助プロセスにおけるアセスメン卜の説明として、適切なものを1つ選びなさい。
1 援助活動の効果を評価する。
2 利用者の課題の達成状況を振り返る。
3 利用者の状況を把握し、社会資源の精査をする。
4 具体的な援助内容を立案する。
5 援助を受ける意思を利用者に確認する。
相談援助の過程は、各段階で何が行われるのかについては、試験でもよく出題される。
必ず、正解したい問題である。
1は、×である。これは、エバリュエーションである。
2は、×である。これはモニタリングである。
3は、〇である。アセスメントでは、利用者の状況を把握し、社会資源の精査をする。
4は、×である。これは、プランニングである。
5は、×である。これはインテークの段階で行われる。
【正解3】
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
個別相談援助の過程は
インテーク(受理面接)→アセスメント→プランニング→インターベンション→モニタリング→エバリュエーション→ターミネーション(終結)
という流れをたどる。
問題42 Hさん(40歳、男性)は、アルコール依存症の入院治療を終え、現在は定期的な外来通院やセルフヘルプグループへの参加を継続している。病棟でHさんを担当していたJ精神保健福祉士は、退院して半年後、Hさんの外来の待合室での様子が気になったことから、「お久しぶり」と声をかけ、面接室で話を聴くこととした。Hさんは、「参加している自助グループの人間関係で悩んだりすることもあるが、トラブルにならないように何とか関係を保てている。今日は話を聴いてもらえてよかった」と語り、J精神保健福祉士はセルフヘルプグループの様子やHさんの気持ちを傾聴した。
次のうち、Hさんの支援過程においてJ精神保健福祉士が行ったこの面接の位置づけとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 プランニング
2 モニタリング
3 エバリュエーション
4 ターミネーション
5 フオローアップ
問題文をよく読んで、状況をしっかりと把握する必要がある。
J精神保健福祉士は、Hが入院治療を受けていたときの病棟でのHの担当者である。
Hは、アルコール依存症の入院治療を終え、現在は定期的な外来通院やセルフヘルプグループへの参加を継続している。この段階で、J精神保健福祉士が行ったこの面接の位置づけであるが、HはすでにJとの援助関係から離れた状態にあるといえる。
そのため、援助関係にあることを前提にしている1,2,3,4は誤りである。
Jが行った面接の位置づけはフォローアップといえる。
【正解5】
問題43 次の記述のうち、精神保健福祉士がクライエントに対して行う面接技法の直面化の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
1 話した内容を別の言葉に換えて簡潔に伝え返すこと。
2 話した内容の矛盾点を見定めて指摘すること。
3 黙っていることの意味をくみとってまとめて話すこと。
4 考えや気持ちを単純な質問で引き出すこと。
5 否定的な内容を肯定的な意味づけに変えること。
面接技法の直面化の意味を知っていた人にとっては極めて簡単な問題である。
⑰問43、⑱問43で出題されている。今後も出題される可能性がある。
1は、×である。これは、言い換え。
2は、〇である。
3は、×である。これは、明確化。
4は、×である。この肢は、閉じられた質問を想起して欲しかったのだと思われる。
5は、×である。これは、リフレーミング。
【正解2】
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス
直面化の他に、励まし、要約と明確化の違い等も押さえておいて欲しい。
特に、面接技法としての励ましは、頑張りましょうといって利用者を励ますことではなく、「利用者の話に関心をもって聴いていることを伝える」ことを指しているので注意しよう。リフレーミングの意味もしっかり押さえておこう。