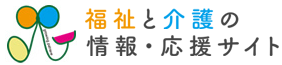問題98 システム理論に基づくソーシャルワークの対象の捉え方に関する次の記述のうち,適切なものを 2つ選びなさい。
1 家族の様々な問題を家族成員同士の相互関連性から捉える。
2 個人の考え方やニーズ,能力を固定的に捉える。
3 個人や家族,地域等を相互に影響し合う事象として連続的に捉える。
4 問題解決能力を個人の生得的な力と捉える。
5 生活問題の原因を個人と環境のどちらかに特定する。
システム理論のシステムとは、人とその環境の相互作用する要素の集合となります。
1:適切
2:個人、固定的などの言葉から不適切であると分かります。
3:適切
4:個人、生得的などの言葉から不適切であると分かります。
5:どちらかに特定などの言葉から不適切であると分かります。
【正解1,3】
問題99 次の記述のうち,ジャーメイン(Germain, C.)によるエコロジカルアプローチの特徴として,最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 空間という場や時間の流れが,人々の価値観やライフスタイルに影響すると捉える。
2 モデルとなる他者の観察やロールプレイを用いる。
3 クライエントのパーソナリティの治療改良とその原因となる社会環境の改善を目的とする。
4 問題の原因を追求するよりもクライエントの解決イメージを重視する。
5 認知のゆがみを改善することで,感情や行動を変化させ,問題解決を図る。
ジャーメイン(Germain, C.)は、ギッターマン(Gitterman,A)とともに、生態学(エコロジー)、エコシステムを主な基本理論とした「生活モデル」を提唱した。
1:適切。人と環境などの社会資源を図にしたエコマップのエコも同じくエコロジーに由来している。
2:説明内容は認知行動療法を想起させる。
3:説明内容は治療モデルや診断主義アプローチを想起させる。
4:説明内容は解決志向アプローチを想起させる。
5:説明内容は認知療法を想起させる。
【正解1】
問題100 ソーシャルワークのアプローチに関する次の記述のうち,最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 ソロモン(Solomon, B.)のエンパワメントアプローチは,人の自我機能に着目し,自己対処できないほどの問題に直面しバランスを崩した状態を危機と捉える。
2 キャプラン(Caplan, G.)の危機介入アプローチは,クライエントが社会から疎外され,抑圧され,力を奪われていく構造に目を向ける。
3 ホワイト(White, M.)とエプストン(Epston, D.)のナラティヴアプローチは,クライエントの生活史や語り,経験の解釈などに関心を寄せ,希望や意欲など,肯定的側面に着目する。
4 リード(Reid, W.)とエプスタイン(Epstein, L.)の課題中心アプローチは,クライエントが解決を望む問題を吟味し,計画的に取り組む短期支援である。
5 サリービー(Saleebey, D.)のストレングスアプローチは,クライエントの否定的な問題が浸み込んでいるドミナントストーリーに焦点を当て家族療法を行う。
人名-理論-説明となっているが、理論と説明の内容が噛み合っていない(交差している)選択肢がある。
1:人の自我機能に着目し,自己対処できないほどの問題に直面しバランスを崩した状態を危機と捉えるのは、キャプランの危機介入アプローチです。
2:クライエントが社会から疎外され,抑圧され,力を奪われていく構造に目を向けるのは、ソロモンのエンパワメントアプローチです。
3:ナラティヴアプローチは、クライエントの生活史や語り,経験の解釈などに関心を寄せます。
クライエントの語るドミナントストーリー(否定的な内容が多い)とはセットと言って良いでしょう。肯定的側面に着目する、という部分が反対となります。
4:適切
5:ストレングスアプローチは、本人の持っている力、できること、に注目するアプローチです。
【正解4】
ソーシャルワンカーと一緒にワン ステップUP‼
ナラティブとは、「物語、語り」という意味であり、利用者の語る物語を通した問題解決の手法である。
利用者がこだわり、思い込んでいる物語(ドミナントストーリー=利用者の支配している物語)に着目して、問題を外在化させ、意外性のあるオルタナティブストーリー(代替の物語)に書き換えていく。
問題101 事例を読んで,Z障害者支援施設のF生活支援員(社会福祉士)が行ったこの段階におけるクライエントへの対応として,最も適切なものを 1つ選びなさい。
〔事 例〕
Gさん(58 歳)は半年前に脳伷塞を起こし左半身に障害がある。現在,社会復帰を目指しZ障害者支援施設に入所している。家族は夫だけだったがその夫は 10 日前に病死した。葬儀が終わり戻ってきたGさんは意気消沈し精神的に不安定な状態だった。さらに不眠も続き食事もとれなくなっていた。そこでF生活支援員はGさんの部屋を訪問した。するとGさんは,「退所後の夫との生活を楽しみに頑張ってきたのに,これから何を目標に生きていけばいいのか」と涙をこらえながら話してくれた。
1 不眠は健康に悪いので日中の活動量を増やすように指導する。
2 悲しみが溢れるときには,気持ちを抑えることはせず,泣いてもいいと伝える。
3 夫が亡くなった現実を直視し,落胆しすぎずに頑張るように励ます。
4 もう少し我慢し耐えていれば,きっと時間が解決してくれると伝える。
5 今までのリハビリの努力を認め,退所後に描いていた生活の一端をかなえるためにも,リハビリに集中するように伝える。
主観的な問題、と言っても良いと思います。 この様な問題は、出題者が何を正解と思っているか、というような観点から解いていきましょう。
1:Gは半年前に脳梗塞を患っているところに唯一の家族である夫が10日前に死亡しているという辛い状況に置かれている。
不眠が続くのも仕方がないであろう。そのようなGに不眠は健康に悪いといった一般的な指導を行うのは不適切である。
2:適切。悲嘆に暮れているGが涙をこらえて話したのに対して、その感情を抑圧せずに表出してよいという対応は、この場面では適切といえる。ネガティブな感情は抑圧されやすいため、それをあえて表現してもらい、利用者自身の内面や問題に向き合えるようにするために、意図的な感情表出を用いるわけである。
3:Gのショックには計り知れないものがある。ましてや死別から10日しか経っていない段階では、夫の死を受け止められないであろう。このような時期に設問のような励ましをすることは不適切である。
4:Gはまだ自分の抑圧された感情を表出しきっていないし、Fのこのような発言は到底受け入れられないであろう。
5:Gに対して、夫の死という辛い状況については考えないようにしようと言っているに等しい発言である。この段階での発言としては不適切である。
【正解2】
ソーシャルワンカーからのワン ポイントアドバイス
Gの置かれている状況をしっかりと把握し、Gの気持ちを推察することが大切である。
その上で、F生活支援員(社会福祉士)はどう対応すべきなのかを考えてみる必要がある。少なくとも、この段階では受容することが優先されるべきだといえる。
意図的な感情表出を知らなかったとしても、選択肢の中でもっとも適切な対応はどれかと問われた場合、センスのある人なら2を選べるはずである。
本問を解く上で役立ちそうな知識には、意図的な感情表出、受容、グリーフケアなどがある。
問題102 相談援助の過程におけるインテーク面接に関する次の記述のうち,ソーシャルワーカーの対応として,最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 クライエントの課題と分析を基に援助計画の作成を行う。
2 クライエントが解決したいと望んでいる課題について確認する。
3 クライエントの課題解決に有効な社会資源を活用する。
4 クライエントへの援助が計画どおりに行われているか確認する。
5 クライエントと共に課題解決のプロセスと結果について確認する。
インテーク面接とは、最も初期の受理面接です。入口部分と言っても良いと思います。
1:プランニングの段階である。
2:適切。インテークの段階で行う。
3:社会資源を活用するのは、インターベンションの実践例である。
4:モニタリングである。
5:エバリュエーションの段階である。
【正解2】
問題103 事例を読んで,U病院のH医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)のクライエントへの対応として,適切なものを 2つ選びなさい。
〔事 例〕
Jさん(26 歳,女性)の 3 歳になる娘は,先天性の肺疾患でU病院に入院中であったが,在宅療養に切り替えることになった。退院に際して,医師はJさんに,「ご自宅で長時間のケアをご家族が担うことになりますので福祉サービスの利用が必要になると思います」と伝え,相談室に行くように勧めた。Jさんは,「今のところ福祉サービスの利用は必要ないと思います」と返答したが,数日後,担当看護師に促されて相談室を訪れた。Jさんは,H医療ソーシャルワーカーに,「自分の子なので自分で看たいと思っています。誰にも任せたくないので,福祉サービスを利用するつもりはありません」と,うつむきながら告げた。
1 Jさんには福祉サービスの利用希望がないので,支援の必要がないと判断する。
2 Jさんに医師の指示なので面接する必要があると伝える。
3 Jさんが相談室に来たことをねぎらい,退院後の生活を一緒に考えたいと伝える。
4 Jさんにカウンセラーからカウンセリングを受けるように勧める。
5 Jさんに自分の役割や相談室の機能などについて説明する。
審判的態度、押しつけ、決めつけなどは禁物。
1:医師は福祉サービスの利用が必要になると考えており、HがJの利用希望のみを聞いて福祉サービスの支援が必要ないと判断するのは適切とはいえない。
2:医師は福祉サービスが是が非でも必要とは言っておらず、それを医師の指示として把えることにも疑問があるし、ましてや医師の指示なので面接する必要があると伝えることにも違和感がある。
3:適切。Jの娘はまだ3歳であり、誰にも任せずに自分で看たいという気持ちもよくわかる。HがそのJの気持ちを受容し、退院後の生活を一緒に考えたいと伝えることは適切だといえる。
4:Jにはカウンセリングを望んでいることを示す発言はないし、カウンセリングが積極的に必要な状況も認められない。
5:適切。Jに相談室に行くように勧めたのは担当看護師であるが、JはそこにいるHが何をする人なのかを十分に理解していないと思われる。そのため、HがJに自分の役割や相談室の機能などについて説明することは適切である。
【正解3,5】
問題104 相談援助の過程における介入(インターベンション)に関する次の記述のうち,適切なものを 2つ選びなさい(ただし,緊急的介入は除く)。
1 介入は,ソーシャルワーカーと医療・福祉関係者との契約によって開始される。
2 介入では,ケース会議などを通じて社会資源の活用や開発を図る。
3 介入は,クライエントや関係者とのパートナーシップを重視して進められる。
4 クライエントのパーソナリティの変容を促す方法は,間接的な介入方法である。
5 コーズアドボカシーは,直接的な介入方法である。
用語を知らなくても慌てない。問題文をよく読めば分かることもある。
1:ソーシャルワーカーと医療・福祉関係者との契約によって開始される、って変です。
2:適切
3:適切
4:クライエントのパーソナリティの変容を促す、のですから間接的とは言えません。
5:コーズアドボカシーは,集団やコミュニティを対象にしたアドボカシーです。直接的な介入とはニュアンスが違います。
【正解2,3】
問題105 相談援助の過程におけるフォローアップに関する次の記述のうち,最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 相談援助が終結したクライエントの状況を調査・確認する段階である。
2 問題解決のプロセスを評価し,残された課題を確認する段階である。
3 クライエントの生活上のニーズを明らかにする段階である。
4 アセスメントの結果を踏まえ,援助の具体的な方法を選択する段階である。
5 クライエントとの信頼関係を形成する段階である。
相談援助の過程のどこですか、フォローアップとは、という問題です。
1:適切。一度終わったものをフォロー(補い助ける)すると覚えれば良いと思います。
2:モニタリング
3:アセスメント
4:プランニング
5:インテーク
【正解1】